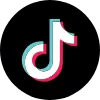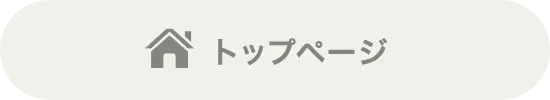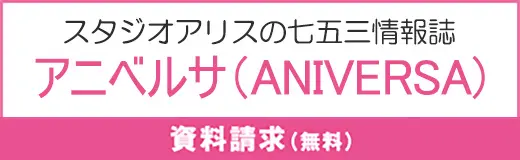お宮参りのご祈祷は必須?ご祈祷に込められた意味や料金について|こども写真館スタジオアリス|写真スタジオ・フォトスタジオ
- TOP
- 撮影メニュー
- お宮参り(ニューボーンフォト)
- お宮参りコラム
- お宮参りのご祈祷は必須?ご祈祷に込められた意味や料金について
お宮参りのご祈祷は必須?ご祈祷に込められた意味や料金について

お宮参りは、赤ちゃんが生まれて1ヶ月を過ぎた頃におこなわれる日本伝統の行事です。お宮参りは神社に参拝するのが一般的ですが、ご祈祷は必ず受けなければならないのでしょうか。
そこで今回は、お宮参りではご祈祷をしてもらったほうが良いのかを、ご祈祷に込められた意味と合わせてご説明します。これからお宮参りを予定している方はぜひ参考にしてください。
お宮参りに込められた意味とは

そもそも、「お宮参りは生後1ヶ月を過ぎた頃におこなうもの」という認識はあっても、お宮参りのご祈祷の本来の意味をご存知の方は少ないのではないでしょうか?
お宮参りとは、赤ちゃんの健やかな成長や長寿を祈っておこなわれる行事のことを指します。医療が十分に発達していなかったために赤ちゃんの死亡率が高かった時代、神社でご祈祷することで「神様からの加護」を受け、元気に成長できるようにという祈りを込めて始まったとされています。
また、お宮参りは赤ちゃんが無事に生まれたことの感謝や赤ちゃんを守ってくれる神様への挨拶という意味も兼ねています。そのため昔は氏神(うじがみ)様という、赤ちゃんの生まれた土地を守ってくれる神様の祀られている神社でしかお宮参りはおこなわれていませんでした。
お宮参りのご祈祷をしなくても大丈夫?

お宮参りは基本的にはご祈祷をしてもらうのが望ましいです。しかし、天候が悪かったり神社が混雑していたり、時間がないなどさまざまな理由でご祈祷をしてもらうのが難しいというケースはあるでしょう。
そこで、ご祈祷なしでおこなうお宮参りの方法を2つご紹介します。ご祈祷をしてもらうお宮参りにこだわらず、ご家族の都合に合わせて適した方法を選びましょう。
ご祈祷なしの参拝方法
まず1つ目は、ご祈祷はせず神社に行って参拝だけおこなう方法です。最寄りの神社で参拝をした場合は、短い時間で済むので赤ちゃんやママに負担がかかりません。
お宮参りの参拝は「二礼二拍手一礼」。通常の参拝方法と変わりませんが、以下で手順を確認しておきましょう。
- 神前で二度深く、丁寧にお辞儀する
- 胸の前で両手を合わせ、ほんの少し右手を下におろして二度拍手を打つ。拍手し終わったら右手は戻す
- 胸の前で両手を合わせてお祈りする
- 最後にもう一度お辞儀する
写真撮影だけおこなう
2つ目は、神社に行かず写真撮影だけおこなう方法です。お宮参り本来の「神様の加護を受ける」「挨拶をする」という意味はなくなってしまいますが、赤ちゃんの成長を記録に残すという意味で、写真撮影だけおこなうご家族も増えてきています。
屋内スタジオであれば天候や気温は関係ないので、赤ちゃんやママへの負担も少なくて済みますし、1ヶ月を過ぎた頃の赤ちゃんを記念に残しておくには、良い思い出になるのでおすすめです。
また、祖父母に撮影した写真をプレゼントすれば思い出を共有でき、親戚や知人に赤ちゃんが生まれたことの報告としても利用できるでしょう。
お宮参りのご祈祷で発生する料金

お宮参りのご祈祷には、初穂料と呼ばれる祈祷料がかかります。当日バタバタしなくて済むように、以下を確認して事前に準備をしておきましょう。
ご祈祷の料金
ご祈祷の料金は、神社によって異なります。大きな神社であればホームページに記載されていることが多いので、事前にチェックしてみると良いでしょう。
しかし、小さい神社ではホームページがなく、電話で問い合わせても「お気持ちで結構です」と言われてしまうことがあります。「お気持ちで」と言われたときは、5,000円~1万円を目安に納めるようにしましょう。基本的には、5,000円で問題ないことがほとんどですが、実家や義実家の地元の神社であれば、祖父母に聞いてみるようにしましょう。
初穂料は、紅白の蝶結びの水引がついているのし袋に入れて納めます。ただし、神社によっては白封筒や茶封筒など、形式が決められているところもあるので、料金とともに事前に確認しておきましょう。のし袋の表面の上部には「初穂料」か「御初穂料」と書き、下部には赤ちゃんの名前を書きます。ご祈祷の際に呼び間違えられてしまう可能性もあるので、赤ちゃんの名前にはふりがなをふっておきます。
事前に予約できるのであれば予約しておく
お宮参りをする神社を決めた後は、事前に予約をしておきましょう。人気がある神社の場合は数ヶ月先まで予約が埋まっていることもあり、ご祈祷をおこなっている曜日や時間が決まっている神社もあります。
また、事前予約が不要でも受付が午前のみというケースもあります。神社に行ってからご祈祷を受けられないということのないようにするためにも、事前に確認と予約をしておきましょう。
お宮参りの一般的な流れ

お宮参りのご祈祷はどのような流れでおこなわれるのでしょうか?以下でお宮参りの流れや、どのタイミングでご祈祷をおこなうのかをご紹介します。
- 1.鳥居
- 鳥居をくぐるところから参拝は始まります。鳥居の前では中央から少し右か左に寄り、一礼してからくぐります。
- 2.参道
- 参道も中央を歩くことは避けましょう。参道の中央部は「正中」という神様の通り道なので、端を歩くのがマナーです。
- 3.手水舎
- 本殿に向かう前に、手や口を清めましょう。右手で柄杓を持って左手をすすぎ、左手に持ち替えて右手をすすぎます。再度右手で柄杓を持って左手に水を溜めたら、その水で口をすすぎ、左手をもう一度すすいで、柄杓を立てて柄を清めます。柄杓を柄杓置きに伏せて置けば終了です。
- 4.受付
- 社務所や総合受付など、お宮参りの受付窓口で申請用紙に記入して受付をしましょう。初穂料はここで納めます。
- 5.待合室
- ご祈祷までの時間は、待合室で過ごします。授乳やオムツ替えは、待合室で済ませておきましょう。ただし、授乳スペースやオムツ替えスペースが用意されていない待合室もあります。事前に確認しておくとスムーズでしょう。
- 6.祈祷
- 家族みんなでご祈祷を受けましょう。
- 7.授与物の受け取り
- 神社によって異なりますが、ご祈祷後にはお札やお守り、お食い初めの器一式などを用意してくれるところもあるので受け取ります。
ご祈祷の基本的な流れ

ご祈祷をおこなう際、基本的な流れは以下のようになります。
- 1.昇殿(しょうでん)
- 待合室でご祈祷の準備が整うまで、待機します。順番が来たら、神職の方の案内に従って社殿に移動します。
- 2.修祓(しゅばつ)
- 神様をお招きする前に、ご祈祷をする人の心身を清めます。神職の方が穢れを清める祓詞(はらえことば)を述べ、大麻(おおぬさ)などで参拝者を祓い、穢れを除きます。
- 3.祝詞奏上(のりとそうじょう)
- 修祓の後は、祝詞奏上に移ります。神様を称え、ご加護をお願いします。
- 4.御神楽(おかぐら)
- 巫女により御神楽がおこなわれます。雅楽に合わせ巫女が舞い、神様に楽しんで頂く意味があります。
- 5.玉串奉奠(たまぐしほうてん)
- 榊などの枝を紙垂(しで)や木綿で巻いたものが玉串です。神様に対しての供物的な意味があり、玉串に祈りを乗せて神様に捧げます。
- 6.神職挨拶・神酒拝戴(しんしゅはいたい)
- 参拝する神社によっては、神職の方に合わせ拝礼をします。報鼓が鳴らされご祈祷は終了します。その後、盃に入った神酒を飲みます。お酒が飲めない人は飲む仕草で問題ありません。
お宮参りのご祈祷を受けるときの注意点

お宮参りのご祈祷を受けるときには、いくつかの注意点があります。代表的な3つの注意点をご紹介するので、参考にしてください。
赤ちゃんがぐずってしまった際の対策
ご祈祷中、赤ちゃんがぐずってしまう可能性があります。立ってあやすことも難しいので、赤ちゃんの気をそらせるためにも音の出ないおもちゃを用意しておくと良いでしょう。
気温の変化への対策をしておく
ご祈祷をおこなってもらう際、気温の変化に対応できるように準備をしましょう。時期によってご祈祷をおこなう本殿や社殿内の気温が、暑いことや寒いこともあります。暑い時期ではハンディクーラーや保冷シート、寒い時期ではブランケットなどを用意しておくと良いでしょう。
赤ちゃんやママの体調には注意する
1ヶ月を過ぎた頃の赤ちゃんはまだ体力がありませんし、産後のママの体調もまだ本調子ではなく、安定していないことがあります。特に赤ちゃんにとって、お宮参りは生後初めての外出となるケースがほとんどなので、十分注意を払ってお宮参りをおこないましょう。
もし少しでも赤ちゃんやママの体調が悪くなったら、無理にお宮参りをせず体調が万全なときにおこないましょう。
ご祈祷の有無関係なしに、お宮参りを良い思い出に

お宮参りのご祈祷は、神様への感謝や挨拶、加護を受けるためにおこなわれる行事です。しかし、事情がある場合はご祈祷なしのお宮参りでも問題ないとされています。今回ご紹介したご祈祷なしのお宮参りの方法を参考にして、無理のない範囲で、みんなが幸せな気持ちになれる方法を選びましょう。
お宮参りコラム一覧
お宮参りのキホン
-
- お宮参りの日取りは大安を選ぶべき?六曜の考え方や準備について紹介
- お宮参りにいく日取りの決め方や六曜で縁起のいい日、当日必要な衣装、マナーについて紹介します。
-
- お宮参りの当日の流れは?ご祈祷にかかる時間や事前準備をチェック
- お祝いの流れや時間帯の決め方など、お宮参りに関する基本情報をまとめて解説します。
-
- これでお宮参りの準備は完璧!
- お宮参り当日の持ち物リスト
-
- お宮参りって何をする?
- マナーや準備などの疑問を解説
-
- お宮参りの参加者は?
- 誰が抱っこする?しきたりやマナーをチェック!
-
- 女の子のお宮参りはいつ?
- 祝い着でとっておきの記念日を
-
- お宮参りは6カ月ずらしてもいい?遅れらせる際の注意点を確認しよう
- お宮参りの時期を遅らせる際の注意点やお宮参りに適した服装、記念写真撮影のタイミングなどに関する疑問にお答えします。
-
- お宮参りに抱っこ紐はいる?
- メリデメで決める「使う」「使わない」
-
- お宮参りの時期はいつまで?
- ずらす場合の注意点と基礎知識も紹介
-
- お宮参りはどこの神社に行く?
- 人気の神社紹介と参拝基礎知識を網羅!
-
- お宮参りや百日祝い(お食い初め)はいつ?1歳までのお祝い行事
- お宮参りや百日祝い(お食い初め)の計算方法と、赤ちゃんが1歳を迎えるまでに行われるお祝い行事について、ママパパが知っておきたいあれこれを深掘りしていきます。
-
- 七五三やお宮参りの初穂料とは?のし袋や中袋の書き方と注意点を解説
- 初穂料に関する情報や、のし袋の書き方を解説します。初めてお宮参りをするママパパに向けて役立つ情報なので、ぜひご一読ください。
-
- 東京の水天宮はお宮参りに最適!人気の理由やご祈祷の流れを解説
- 水天宮へお宮参りする際のポイントやご祈祷の流れについてまとめました。
-
- お宮参りの祖父母のお祝い金相場は?マナーを知って楽しくお祝いしよう
- お宮参りにおける祖父母のお祝い金について、金額の相場やマナーを踏まえて紹介します。
-
- お宮参り当日に雨が降ったらどうする?対処法や写真の撮り方のコツを紹介
- お宮参りが雨の場合の対処法や写真の撮り方のコツ、延期するときの注意点などを紹介します。
-
- お宮参りの紐銭・帯銭とは?結び方や意味、どこに売っているかをチェックしよう
- 紐銭・帯銭とはどのようなものか、また結び方などについて紹介します。
-
- 初穂料とは?玉串料との違いやマナー、必要な場面をチェックしよう
- 初穂料の言葉の意味やマナー、初穂料が必要なさまざまなシチュエーションや金額目安などについて解説します。
-
- 「初宮参り」では何をする?基礎知識をおさらいしよう
- 初宮参りに関するさまざまな知識をお届けします。
-
- お七夜とはどんな行事でいつやるの?お祝いの方法やマナーを解説
- お七夜とはどんな行事なのか、誰がいつやるのかなどについて詳しく解説します。
-
- ニューボーンフォトをかわいく手作り!コスパ抜群アイテムも紹介
- ニューボーンフォトにおすすめの手作りアイテムや撮影時の注意点を中心に解説します。
-
- 赤ちゃんの命名式や出生届はいつまでにやる?やり方とお七夜の意味を知ろう
- 命名式やお七夜はいつ、何をするものなのかという基本情報に加えて、出生届の期限についても解説します。
-
- 命名書の書き方やお宮参りで困らない!準備や作法のポイントを紹介
- 命名書とお宮参りの基礎知識や準備・作法について紹介します。
-
- ニューボーンフォトは生後何日までに撮る?おすすめポーズや小物を紹介
- ニューボーンフォトは生後何日までに撮るか、撮影の注意点やおすすめのポーズ・小物などを紹介します。
-
- ニューボーンフォトをご家族で撮影しよう!ポイントやおすすめポーズを紹介
- ご自宅でのセルフ撮影とスタジオ撮影の違い、ニューボーンフォトの魅力や注意点を紹介します。
-
- ベビーフォトをセルフで撮ろう!自宅で撮影するコツや時期・注意点
- ベビーフォトをセルフで撮影する方法を紹介します。
-
- ニューボーンフォトで赤ちゃんが寝ない問題を解決!対策やアイデアは?
- ニューボーンフォト撮影時に赤ちゃんが寝ない場合の対策や、ニューボーンフォトならではの注意点などを紹介します。
-
- 犬張子とは?由来や発祥、お宮参りの小物に込められた意味
- 「犬張子(いぬはりこ)」の由来や発祥、小物に込められた意味を紹介します。
-
- 初参りとお宮参りの違いは?お祝いの基本情報やおすすめの神社やお寺を紹介
- お宮参りとの違いや初穂料をはじめ、初参りに関する基本情報を解説します。
-
- 新生児が毛深い理由を徹底解説!背中やおでこの濃い産毛はいつまで続く?
- 新生児が毛深い理由について詳しく解説します。
-
- お七夜のお祝いはいつ何をする?数え方や用意など気になる疑問を解消
- いつお七夜をするのかというテーマを中心に、お祝いの仕方や命名書の書き方などを詳しく紹介します。
-
- お七夜のお祝いの仕方は?命名式や命名書の書き方もチェックしよう
- お七夜のメインとなる命名書の書き方をはじめ、お七夜に関するさまざまな疑問にお答えしています。
-
- お宮参りの場所はどこにする?選び方のポイントやマナーを紹介
- お宮参りの場所を決めるポイントについて解説します。
-
- お宮参りの食事会であいさつは必要?例文や気持ちが伝わるコツを紹介
- 食事会でのあいさつのポイントや例文、気持ちを伝えるためのコツを解説します。
-
- お七夜はどちらの実家でやる?お祝い方法や費用など気になる疑問を解消
- 赤ちゃんが誕生して最初の行事である「お七夜」について解説します。
-
- お七夜はケーキで華やかにお祝い!選び方とメッセージを紹介
- お七夜に用意するケーキの選び方やヘルシーケーキのアイデアを紹介します。
-
- お七夜に祖父母が参加する際のお祝い金の相場は?招くときの注意点も
- お七夜のお祝い金の相場を解説するとともに、ママパパがもらってうれしいおすすめのプレゼント、またお祝い金を渡すポイントを紹介します。
-
- お七夜をする・しないで迷っているママパパは簡単なお祝いで記念を残そう!
- お七夜について解説するとともに、お七夜をしないという選択はありかという疑問を解消します。
-
- ベビーカーや抱っこひもでお宮参りに行ってもよい?注意点を確認しよう
- お宮参りにベビーカーや抱っこひもを利用するときの注意点を紹介します。
-
- お宮参りのバッグはどう選ぶ?服装選びのポイントや必需品もチェック
- お宮参りにふさわしいバッグについて紹介します。
-
- お宮参りは2回してもいい?場所や日程の決め方、注意点を解説
- お宮参りを2回するケースについて紹介します。
-
- 喪中にお宮参りの時期が重なったときはどうする?マナーや注意点をチェック
- お宮参りと喪中が重なったときの対応にフォーカスします。
-
- お宮参りをしない選択はNG?やっておきたい理由とできない原因の解消方法
- お宮参りをおすすめする理由や、お参りができない原因の解消方法などを紹介します。
-
- お七夜のお祝い方法は?命名式に必要な命名書の書き方や残し方
- お七夜や命名式に関するさまざまな情報をまとめました。
-
- お宮参りで赤ちゃんにケープは必要?選び方や使い道を解説
- お宮参りに用いるケープに関する疑問をまとめました。
-
- お宮参りの服装にはよだれかけが必須!ポイントを押さえ最適な1枚を選ぼう
- よだれかけ選びのポイントをはじめ、後半ではお宮参りの注意点についてもまとめました。
-
- お宮参りは1カ月検診前にいってもよい?日程の決め方や準備
- お宮参りは1カ月検診前に行ってもいいのかという疑問にフォーカスしました。
-
- 産土神社調べは無料でできる?探し方とお宮参りでの参拝方法お宮参りのキホン
- 産土神社の探し方やリサーチにかかる費用について解説します。
-
- お宮参りの歴史を知ろう!基本情報や現代のスタイルも紹介
- お宮参りの歴史について解説します。
-
- 初宮参りの日と仏滅が重なったら?六曜の考え方や日程調整のポイント
- 仏滅や六曜の考え方、初宮参りのタイミング、仏滅との関係について詳しく解説します。
-
- ニューボーンフォトがたまらなくかわいい!セルフ撮影するなら注意点を把握
- ニューボーンフォトをセルフ撮影する際のポイントを紹介します。
-
- 【2023年版】お宮参りにベストな日取りチェック表!決め方のポイントも◎
- お宮参りの日取りはどのようなポイントを考慮すればいいのか、という点を深掘りします。
-
- お宮参りで赤ちゃんが着る産着・祝着(のしめ)の柄に込められた意味は?
- お宮参りの基礎知識を紹介するとともに、お宮参りで赤ちゃんの正装とされる産着・祝着(のしめ)の柄に込められた意味や選び方を紹介します。
-
- 仏滅にお宮参りをしてもいい?六曜との関係性や日程調整のポイント
- 仏滅とお宮参りとの関係性や六曜の意味、日程調整のポイントを紹介します。
お宮参りの服装・ヘアアレンジ
-
- お宮参りの着物の選び方は?和装を含めた赤ちゃん・ママパパの衣装を詳しく解説
- お宮参りに最適な和装はどのようなものかを解説します。
-
- お宮参りではどんな着物が良いの?
- パパ・ママ・赤ちゃん別におすすめの着物や選び方をご紹介!
-
- 男の子のお宮参りは着物が定番?
- 着物の選び方や柄の意味を解説
-
- 【お宮参り】着物レンタルと購入の相場を解説!
- レンタル・購入した場合のメリットとは
-
- お宮参りでの髪型やマナーとは?
- おすすめのヘアスタイルやメイクを紹介
-
- お宮参りでのママの服装はどうすればいい?
- おすすめのママコーディネート4選
-
- お宮参りのベビードレスの選び方や着せ方を解説!
-
- お宮参りの男性の服装は?スーツやネクタイの選び方やマナーを紹介
- 赤ちゃんの生後30日前後のお祝いであるお宮参りにおいての、男性の服装について詳しく解説します。
-
- お宮参りの小物は必要?
- 種類や意味、入手方法を紹介
-
- お宮参りの服装は洋装?和装?
- 季節ごとのスタイルや注意点も紹介!
-
- お宮参りの靴はフォーマルが基本!服装の決め手は靴選びがポイント
- お宮参りにふさわしい靴について紹介します。
-
- 夏のお宮参りは快適な服装で!暑さ対策のポイントと便利グッズを紹介
- 夏のお宮参りにおすすめの服装を赤ちゃんとご家族ごとに紹介します。役立つ夏の暑さ対策グッズや、気を付けておきたいことについても解説します。
-
- お宮参りの祖父母の服装ガイド|服装選びのポイントや注意点を解説
- お宮参りの祖父母の服装について、年代別や季節感に合わせた選び方を紹介します。
-
- お宮参りで母親(ママ)は何を着る?衣装はレンタルがベスト?
- お宮参りのママの服装について解説します。
-
- お宮参りの着物の着せ方をチェック!早めの準備が成功のポイント◎
- お宮参りの着物・祝着(のしめ)の着せ方から購入やレンタルといった手配の仕方まで、準備しておきたいポイントを詳しく解説します。
-
- 和装でお宮参り|母親(ママ)やご家族はどんな着物を着る?
- お宮参りに行く母親(ママ)にふさわしい着物の種類を紹介します。
-
- 【お宮参り】私服でも問題ない?コーデの選び方や注意点を紹介
- お宮参りにマッチする私服選びのポイントや注意点、赤ちゃん・ママパパのコーデ例を紹介します。
-
- お宮参りの紐銭のつけ方は?おすすめのひもやお返しについての疑問も解決!
- 紐銭がどのようなものかについて解説します。
-
- お宮参りの祖母の服装|選び方のポイントは?マナーや注意点を知ろう
- お宮参りで祖母が服装を選ぶ際のポイントを解説します。
-
- お宮参りは産着・祝着(のしめ)なしでも大丈夫?ママパパの疑問を解決
- お宮参りで赤ちゃんが祝着(のしめ)を着用する際の着せ方を紹介します。用意した着物にひもがないときの対処法も確認しておきましょう。
-
- お宮参りの着物は誰が買う?費用目安やその他に必要な費用をチェック
- お宮参りの着物をはじめとする気になる費用相場や、お宮参りに選びたい男の子・女の子の着物について紹介します。
-
- お宮参りの祝着(のしめ)や着物でよく耳にする友禅とは?
- 友禅染めの種類や魅力、祝着(のしめ)やママの着物に向いている柄などを紹介します。
-
- 3歳の夏は浴衣で思い出を!夏の和装の種類と選び方のポイント
- 3歳のお子さま向けの浴衣の選び方や基礎知識について紹介します。
-
- 戌の日の安産祈願に腹帯は持参する?持ち込み方やおすすめの腹帯についても紹介
- 安産祈願の腹帯の持参について解説します。
-
- お宮参りで着物を着る際の授乳方法とは?必需品や注意点も紹介
- 授乳期間中に着物でお宮参りをするときのポイントや、準備しておくと助かるアイテムについてまとめました。
-
- お宮参りにふさわしい祖母の着物とは?年代や季節別のおすすめを紹介
- お宮参りに適した着物の選び方、祖母の年代、季節ごとの選び方を紹介します。
-
- 【お宮参り】両親の服装はどうする?選び方のポイントやマナーを解説
- お宮参りに参列する際に適したご家族の服装の選び方について、マナーを交えながら紹介します。
-
- お宮参りに訪問着を着たいママ必見!選び方のポイントと注意点
- お宮参りに着る訪問着について紹介します。
-
- お宮参りの産着の下は何を着る?赤ちゃんの服装について確認しよう
- お宮参りの産着の下に着る服装について特集します。
-
- お宮参りの産着の柄に込められた意味とは?縁起を担ぐ小物の意味も◎
- お宮参りの産着の柄に込められた意味を解説します。
-
- お宮参り|赤ちゃんに帽子はいらない?選び方や服装のマナー徹底ガイド
- お宮参りでの帽子の必要性や選び方、服装マナーについて詳しく解説します。
-
- お宮参りで上の子の服装に悩んだら?選び方のポイントや服装例をチェック
- お宮参りに同行するごきょうだいの服装について、選び方を解説します。
-
- お宮参りに袴ロンパースはアリ?おすすめの服装と選び方のポイント
- お宮参りに袴ロンパースはアリかという点を解説するとともに、おすすめの衣装や服装の準備方法も併せて紹介します。
お宮参りのお祝い
-
- お宮参りのお祝い金の相場はいくら?
- お祝いの包み方や渡すタイミングとは
-
- お宮参りの内祝い
- ~内祝いの選び方やマナーを知ってお宮参りに臨みましょう!~
-
- お宮参りに手土産は必要?祖父母へのおすすめ手土産や内祝いについて解説
- お宮参りの際に準備する手土産について、シーン別に紹介します。
お宮参りでのご祈祷
-
- お宮参りでかかるお金を徹底解説!
- お祝い金や初穂料などの相場とは?
-
- お宮参りの初穂料(お金)はいくら?のし袋や封筒の正しい書き方やマナーを解説
- お宮参りの初穂料(お金)を包むのし袋や封筒の正しい書き方やマナーを解説。
-
- お宮参りのご祈祷は必須?
- ご祈祷に込められた意味や料金について
-
- 初穂料は連名でもOK?お子さまの行事で役立つマナーを解説
- お子さまの行事で渡す初穂料は連名で書けるのか、のし袋への書き方や渡す際のマナーなどを紹介します。
-
- 初穂料はふくさに包むのがマナー!ふくさの色やのし袋の書き方も確認しよう
- 慶事に欠かせない初穂料、初穂料を包むふくさについて詳しく紹介します。
-
- 初穂は中袋なしでもOK?のし袋の書き方やマナーを知ろう
- 初穂料を包むのし袋について解説します。
-
- 産土神社でのお参りの仕方は?知っておきたい参拝の作法とマナー
- 産土神社でのお参りの仕方について解説します。
-
- 先負とは?六曜の意味やお祝いごとに最適な時間帯を詳しく解説します
- 「先負」の日を詳しくチェックするとともに、六曜の意味や由来、そして現代での活用法について解説します。


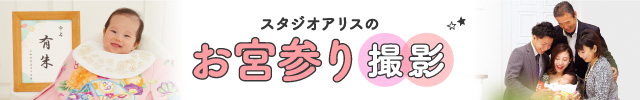









![家族の思い出に、もっとフォーカス[PINTO]](/common/img/bnr_recommend_pinto.jpg)