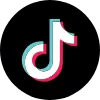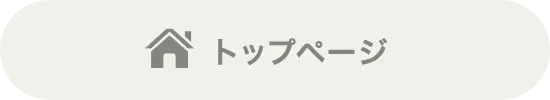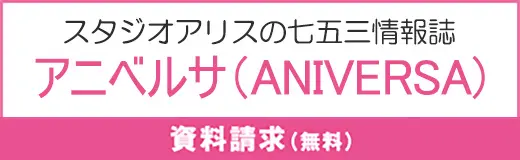女の子の七五三はいつやるの?可愛さ引き立つ女の子向け衣装の選び方|マタニティ、赤ちゃん、こどもの記念写真撮影ならこども写真館スタジオアリス|写真スタジオ・フォトスタジオ
女の子の七五三はいつやるの?
可愛さ引き立つ女の子向け衣装の選び方

お子さまの成長をお祝いする行事のひとつに、七五三があります。3歳、5歳、7歳の節目にお詣りをし、着物やドレスなどの衣装を着て写真を撮ったり、ご家族や親族と会食をしたりしますが、七五三をするタイミングや、年齢に合った衣装などを悩まれるお父様やお母様も多いのではないでしょうか。
今回は、女の子が七五三をするタイミングや一般的な流れ、衣装の選び方などをご紹介します。女の子の七五三についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
- 目次
- 女の子の七五三は何歳にするのがベスト?
- 七五三のお祝いをする年齢
- 七五三のお詣りや撮影のおすすめの時期は?
- お詣りする日程の決め方
- 知っておきたい!七五三の一般的な流れ
- 女の子の七五三に適した服装は?
- 3歳の女の子におすすめの衣装と選び方
- 7歳の女の子におすすめの衣装と選び方
- 一生の思い出!女の子の七五三撮影はスタジオアリスで
- まとめ
女の子の七五三は何歳にするのがベスト?
お子さまが1歳を過ぎると、「七五三はいつやればいいの?」と気になり始める方も多いのではないでしょうか。古くから「七五三は数え年でするもの」といわれていますが、最近では「満年齢で七五三をしても問題ない」ともいう考えもあり、七五三の時期には、明確な正解はなく、ご家庭によってさまざまです。
ここでは七五三を祝う年齢について、満年齢や数え年、早生まれなどの観点から解説します。
七五三のお祝いをする年齢

七五三は、古来に行われていた3歳「髪置きの儀」、5歳「袴着(はかまぎ)の儀」、7歳「帯解(おびとき)の儀」に由来するもので、現在も3歳、5歳、7歳にお祝いをします。
女の子は3歳と7歳、男の子は3歳と5歳(5歳のみ、という説もあり)の儀式をするとされており、現在の七五三のお祝いも女の子は3歳と7歳でするのが一般的です。
数え年と満年齢のどちらで祝う?
七五三のお祝いをする3歳、5歳、7歳ですが、昔は満年齢ではなく「数え年」で行うのが正式とされていました。
「数え年」とは、生まれた年を1歳とし、新年(1月1日)を迎えると1つ歳をとるという年齢の数え方です。この数え方では、12月生まれの子は翌年の1月には2歳とされます。
しかし政府の方針もあり、第二次世界大戦以降から現在にいたるまで、誕生日で加齢する「満年齢」が一般的です。数え年で11月15日に七五三を祝う場合、満年齢では2歳、4歳、6歳になる年にお祝いすることになります。
現在では、七五三を含む主な年祝いでは数え年、満年齢のいずれで行ってもよいとされています。ただ、地域によっては今でも七五三は数え年で行うのが一般的なところや、世代の離れた祖父母は考えが違うという場合もありますので、ご家族と相談しながら決めるといいでしょう。
早生まれの場合は?
年齢でもうひとつ気になるのが「早生まれ」のお子さまの場合です。早生まれとは1月1日~4月1日の間に生まれた人のことで、学校教育では同年生まれの子よりもひとつ上の学年に組み込まれます。
早生まれのお子さまが満年齢で七五三を行う場合は次年度の11月になるため、早生まれではない同級生と一緒にお祝いできなくなります。
「数え年」「満年齢」「早生まれ」と考えるポイントがいくつかあり、ややこしく思えてしまいますが、現代の七五三では行うべき時期が明確に定められているわけではありません。
七五三のお祝いをする年齢のころは、お子さまの成長に個人差が大きくなります。特に3歳の場合は、数え年だとまだ1,2歳で長時間の和装や神社での儀式に耐えられなかったり、トイレトレーニングの最中で心配事が多かったり、お昼寝の時間との調節が大変だったりするでしょう。
最近では満年齢でお祝いすることが主流となっていますが、早生まれのお子さまの場合は同級生と一緒にお祝いすることも多く、数え年を選ばれるご家庭もあります。そのころのお子さまの成長や状況を考え、臨機応変に時期を選ぶのが現代の七五三のやり方といえるのではないでしょうか。
2019年~2024年の七五三年齢早見表
| 3歳(数え年) | 3歳(満年齢) | 5歳(数え年) | 5歳(満年齢) | 7歳(数え年) | 7歳(満年齢) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 (令和元年) |
2017年 (平成29年) |
2016年 (平成28年) |
2015年 (平成27年) |
2014年 (平成26年) |
2013年 (平成25年) |
2012年 (平成24年) |
| 2020年 (令和2年) |
2018年 (平成30年) |
2017年 (平成29年) |
2016年 (平成28年) |
2015年 (平成27年) |
2014年 (平成26年) |
2013年 (平成25年) |
| 2021年 (令和3年) |
2019年 (令和元年) |
2018年 (平成30年) |
2017年 (平成29年) |
2016年 (平成28年) |
2015年 (平成27年) |
2014年 (平成26年) |
| 2022年 (令和4年) |
2020年 (令和2年) |
2019年 (令和元年) |
2018年 (平成30年) |
2017年 (平成29年) |
2016年 (平成28年) |
2015年 (平成27年) |
- ※早生まれの場合も上記表と同じです。ただ、同じ学年のお友達と一緒に七五三をお祝いしたい場合は、「早生まれではない同級生=満年齢、早生まれのお子さん=数え年」で行うと同じ年にできます
女の子は5歳で七五三をしてはいけないの?
男女の別も古来の儀式に倣って3歳男女、5歳男の子、7歳女の子でお祝いする形が一般的ですが、地域によって異なる場合もあります。
最近では、3歳は女の子のみお祝いするところも多くあります。また、兄弟や姉妹、お友達と一緒にお祝いするというご家庭も多く、5歳で女の子、7歳で男の子のお祝いをする場合も多いようです。そのため、「女の子が5歳で七五三をしてはいけない」ということはありません。
また、11月16日から12月31日までに生まれた女の子が数え年で七五三をすると、満年齢では5歳ということになります。
現代ではご家庭やお子さまの事情に合わせた柔軟なスケジュールが大切とされており、正式な形に捉われすぎず、お子さまの成長や兄弟姉妹の年齢差、周りの環境などを考え合わせてベストな時期を選ぶことをおすすめします。
11月15日に七五三を行う場合の数え年・満年齢対応表
| 1月1日~11月15日生まれの場合 | |||
|---|---|---|---|
| 数え年 | 3歳 | 5歳 | 7歳 |
| 満年齢 | 2歳 | 4歳 | 6歳 |
| 11月16日~12月31日生まれの場合 | |||
|---|---|---|---|
| 数え年 | 3歳 | 5歳 | 7歳 |
| 満年齢 | 1歳 | 3歳 | 5歳 |
七五三のお参りや撮影のおすすめの時期は?

神社などで七五三のお祝いやご祈祷をする日は、一般的には11月15日です。この前後になると神社は大変混雑します。加えてママ・パパのお仕事の都合もあるため、近年は11月15日の前後1、2ヶ月に参拝をする、写真を撮るという方が多いようです。
この時期は一年のなかでも過ごしやすく、紅葉も見頃のシーズンとなります。よって七五三のお詣り撮影は、美しい紅葉を背景にお子さまのベストショットが期待できる9月~12月初旬くらいでご家族の都合がよいタイミングに設定するとよいでしょう。
ただし、早い時期にお詣りする際は気温に注意しましょう。9月、10月のうちは突然暑くなる日があるため、お子さまは慣れない着物で余計に暑くなってしまい、体調を崩してしまうこともあります。
一方で寒冷地に住んでいる方は、11月末になると気温が下がり風邪を引いてしまう、雪が降り足元が悪くなると着物が汚れたり怪我をしたりすることがあるため、早めにお詣りをするのがおすすめです。
お詣りする日程の決め

お詣りの日程は11月15日当日にこだわらず、ご家族の仕事の都合などを調節し、秋の吉日の週末を選ばれる方が多いようです。
しかし、週末はやはり混み合い、ご祈祷待ちの時間も長くなる場合があります。ご家族の予定にもよりますが、お詣りの日程は平日に設定するのがおすすめです。混雑していない境内は歩きやすく、写真撮影もゆっくりできます。そして、お子さまのペースや万が一のトラブルにも対応しやすくなります。
また、七五三撮影の日取りやレンタル衣装の予約日などからお詣り日を決める場合もありますが、平日割引をしているお店もありますので、予算面から日取りを考えてみるのもよいでしょう。
日取りを決める際には「六曜」を参考にされる方も多くいらっしゃいます。六曜とはその日の吉凶や運勢などを表す暦注の1つで、「先勝」「友引」「先負」「仏滅」「大安」「赤口」の6種類があります。大安は慶事を行うのによい日とされていますが、時間帯によっては他の六曜も吉日となります。
六曜とは?
| 大安たいあん | 「泰安」が元になっており、「大いに安し」の意味。六曜のなかで最も縁起がよいとされ、一日中吉日です。何事においてもよいとされ、七五三を祝うのに最も適した日といえます。 |
|---|---|
| 友引ともびき | 元は「共引き」を意味し、「友」に幸せを「引く」として大安に次ぐ吉日。七五三のお祝いにも向く日ですが、朝夕が吉、昼(11時~13時ころ)は凶とされるので正午前後を避けてお詣りするのがよいでしょう。ちなみに、陰陽道の「友引日」と混同して「友」を冥土に「引く」という意味も加わり、葬儀などを行うにはよくない日とされています。 |
| 先勝せんしょう・ せんがち・ さきがち |
六曜では3番目の吉日。「先んずれば即ち勝つ」の意味で何事も急ぐことをよしとした日です。午前が吉、午後が凶とされるので、七五三のお詣りは午前中に済ませるのがよいでしょう。 |
| 先負せんぶ・ せんまけ・ さきまけ |
先勝とは逆の意味を持つ日。「先んずれば即ち負ける」の意味で何事も急がず、平静を守ることがよいとされます。午前が凶、午後が吉とされるので、午後からゆっくりとお詣りされたい方におすすめです。 |
| 赤口しゃっこう・ しゃっく |
昼(11時から13時ころ)のみを吉とし、その他の時間帯は凶とする、仏滅に次ぐ凶日。赤舌神という鬼人が支配する陰陽道の「赤舌日」と混同され、大事を行うにはよくない日とされています。七五三をこの日にする場合は正午前後にお詣りをするとよいでしょう。 |
| 仏滅ぶつめつ | 六曜のなかで最も縁起が悪いとされる大凶日。元はあらゆるものが滅びる「物滅」と表記されていましたが、仏さえも滅するという意味で「仏滅」に転じました。一日中凶とされ、特に慶事を行うには不向きとされています。 |
このように吉日、凶日を表す六曜ですが、仏教との関連やはっきりとした根拠もないため、占いや迷信の類ともいえます。解釈も一本化されておらず、さまざまな説が存在しますので、信じるかどうかは人それぞれでしょう。
七五三では六曜より11月15日の正式な日取りを優先される方、仏滅でも逆に混雑していなくてよいと考える方もいます。何事も絶対的な決まりはありませんので、ご家庭で大切にしたい優先事項に従って決めるのがおすすめです。
知っておきたい!七五三の一般的な流れ
七五三の流れとして、まず前撮りをし、その後神社などで参拝、そしてご家族や親族で集まって会食をするというのが一般的な流れです。最近では記念撮影のみをする、前撮りと参拝の時期をずらすなど、ご家庭によってさまざまなスタイルで七五三のお祝いをすることが増えています。
女の子の七五三に適した服装は?
お子さまの成長を喜びお祝いし、長寿を祈願する七五三ですが、お祝いの行事ということで和装やドレスなどの特別な服装で神社に参拝するご家庭が多いでしょう。
女の子の七五三は3歳と7歳でするのが一般的ですが、着物は年齢に適したものを選ぶとよいとされています。では、それぞれの年齢にふさわしいタイプの着物やその他の服装は、どのようなものがあるのでしょう。
3歳は「三つ身」の着物
七五三には和装をする女の子も多いですが、3歳では「三つ身」というタイプの着物を着て、帯はやわらかな兵児帯(へこおび)を締め、さらに被布(ひふ)と呼ばれる、袖のないベスト状の上着を着るのが一般的です。
3歳の着物は小さなお子さまの愛らしさが際立つデザインで、子どもらしい印象を全面に押し出してくれます。
ひもや帯など、締め付けの強いものを使用しないため小さなお子さまへの負担も軽く、また着付けがしやすく、着崩れしにくいというのもうれしい点です。
7歳は「四つ身」の着物
7歳の七五三では、3歳のときとは異なる「四つ身」というタイプの着物を着ます。四つ身は子どもサイズの大人用の着物というイメージで、必要な小物や着付けの方法などは大人と同じです。
着付けの際には襦袢や半襟、帯、帯揚げ、帯締めなどが必要で、また扇子や筥迫(はこせこ)といった小物も増えます。また、しっかり着付けないと着崩れしてしまう、着付けに慣れていないとお子さまに負担がかかってしまうため、プロに依頼するのがおすすめです。
ワンピースなどの洋装もOK
和装が一般的ではありますが、ワンピースなどの洋装で七五三のお祝いをするご家庭もあります。洋装の場合は、神様の前でご祈祷を受けるということを忘れず、普段着ではなくフォーマルなワンピースやスーツを選びましょう。
スタジオ撮影では、多くの女の子が憧れるお姫様のようなドレスも人気があり、天候やお子さまの年齢、成長の様子などを見て、洋装、和装どちらにするか判断するとよいでしょう。
3歳の女の子におすすめの衣装と選び方
3歳の女の子が和装をする場合には、できるだけ軽い生地のものを選ぶことが大切です。重い生地の場合、小さなお子さまには負担が大きくなってしまうこともあります。
なかには着付けをいやがって、泣いたりじっとしていられなかったりするお子さまもいますので、その際は無理に和装を選ばず、負担が少なく着脱も楽な洋装にしましょう。
和装は購入する場合もありますが、前撮りやお詣りのときだけレンタルをするご家庭もあります。レンタル衣装を汚してしまうかもしれないなどの心配がある際は、スタジオで前撮りをし、お詣りの当日は自宅にあるフォーマルなワンピースを選ぶと安心です。
3歳の女の子の場合、衣装のデザインや柄などはご両親や祖父母など、ご家族が選ぶ傾向にありますが、和装は赤など明るくはっきりとした色合いのものや、かわいらしさのある古典的な柄、洋装も明るい色のものが人気です。
7歳の女の子におすすめの衣装と選び方
7歳の七五三には女の子が着物の帯をつけ始めるという意味があること、また3歳のときよりも落ち着いていられることから、前撮りだけでなく参拝時にも振り袖を着ることが多いです。
3歳の衣装は、はっきりとした色合いやかわいらしい柄が人気ですが、7歳は見た目もお姉さんらしくなり、お子さま自身も少し背伸びをしたいお年頃でもあるため好みが分かれます。
赤やピンクなどの可愛い着物ももちろん人気がありますが、青や紫、緑といった大人っぽさ、落ち着きのある色合い、レトロモダンな柄の着物も選ばれることも少なくありません。
洋装で参拝に行くという方もいますが、どちらかというと洋装は、和装の前撮りの際にドレス撮影もする、というパターンが多いようです。ドレスもお姫様のようなものから落ち着いた印象のものまで豊富にそろっています。お子さまの好みに合わせて選ぶのが主流です。
一生の思い出!女の子の七五三撮影はスタジオアリスで

女の子の七五三は、洋装も和装も可愛い衣装が多いですが、お子さまのご機嫌や体調、長時間衣装を着ていることが難しい、レンタル衣装を汚してしまうかもしれないなど不安も少なくありません。
スタジオアリスの七五三撮影は、豊富な衣装やお子さまの撮影に慣れているプロのカメラマン、おでかけ衣装のレンタルなど、さまざまな魅力があります。
また、スタッフの検温やマスク着用はもちろん、店内の消毒、換気など感染予防対策を徹底していますので、コロナ禍でも安心して七五三の思い出を残していただくことが可能です。
(参考:『スタジオアリス』ホームページ)
種類が豊富!好みの衣装が見つかる
スタジオアリスには約470着の衣装がそろっていますので、普段着でご来店いただけます。和装と洋装の組み合わせなど、お好きな衣装を複数選んでの撮影が可能です。おひとり、ご兄弟と一緒に、ご家族勢揃いで、さまざまなスタイルで撮影をお楽しみください。
バリエーション豊富な衣装のなかには、お子さまに人気のキャラクターとコラボした和装もあり、大切な記念のお写真を、お子さまが大好きなキャラクターたちで華やかに彩ります。
着付けやヘアアレンジもおまかせできる
七五三の着付けやヘアセットに悩まれるママ・パパも多いですが、スタジオアリスなら着付けやヘアアレンジをトータルでおまかせいただけます。ヘアセット一覧表から、衣装にぴったりのお気に入りのヘアアレンジをお決めください。また、ご希望のお子さまには簡単なメイクをすることも可能です。
おでかけ用着物もレンタル可能
「せっかくだから神社にも着物でお詣りに行きたい」そんなお客様の声にお応えできるよう、スタジオアリスではおでかけ用着物をレンタルしています。人気ブランドやキャラクター衣装など、多様なデザインのなかから選ぶことができ、レンタルする着物は撮影時と違う衣装でもOKです。
「おでかけ当日の着付け、ヘアセットは無料で、髪飾りや草履などもレンタル可能なので、撮影時同様、手ぶらでお越しご来店いただけます。
「また、普段なかなか着る機会のない着物を着て七五三の撮影をする、というママ・パパも増えてきました。
「日本の伝統である和装をご家族で楽しめるよう、大人も手ぶらでご来店、店内で着付けをする「パパママ着物フォトプラン」も用意しています。着物も小物もすべてレンタル可能ですので、ぜひお子さまの記念日に、ご家族そろって和装での写真を残してみてはいかがでしょうか。
まとめ

七五三の女の子の衣装に和装を選ぶ家庭も多いですが、3歳と7歳では着物の種類や人気の色、柄も異なります。洋装の場合、神社に行く際はフォーマルなワンピースがおすすめですが、前撮りではお姫様のようなドレスを着て記念の写真を残される方も少なくありません。
スタジオアリスでは和装、洋装どちらの撮影ができ、キャラクターコラボの衣装や、お出かけ用着物のレンタルも用意しております。
兄弟、ご家族と一緒に、ぜひスタジオアリスで七五三の記念の撮影をお楽しみください。皆様のご来店をお待ちしております。
七五三コラム一覧
七五三のキホン
-
- 七五三の意味や由来って?今さら聞けない基本的な疑問や流れ・服装を解決!
- 七五三の意味や参拝に行く場所、七五三の儀式に必要な準備や適切な服装などを紹介します。
-
- 女の子の七五三はいつやるの?可愛さ引き立つ女の子向け衣装の選び方やおすすめの時期
- 女の子が七五三をするタイミングや一般的な流れ、衣装の選び方などを紹介します。
-
- 七五三って何をする行事?基礎知識から気になる疑問をまとめて解説!
- 七五三をお祝いする時期や当日の流れ、必要な持ち物を紹介しながら、七五三はいったい何をする行事なのか詳しく説明します。
-
- 七五三をお祝いしよう!年齢ごとの衣装選びや準備、3歳の七五三をスムーズにするコツも◎
- 七五三について年齢別のおすすめ衣装や準備のポイントと併せて、やんちゃ盛りのお子さまでも楽しく、かつスムーズにお祝いの日を過ごせるコツを紹介します。
-
- 七五三を兄弟姉妹で同時にするメリット|服装・写真撮影を徹底ガイド
- 兄弟姉妹で一緒にする場合のメリットを解説しながら、当日の服装や写真撮影についてご紹介します。
-
- 七五三当日の流れは?記念写真撮影は前撮り・後撮りも活用しよう
- 七五三当日の流れや、スムーズなお祝いをするためにおすすめしたいスタジオアリスの七五三撮影の魅力をご紹介します。
-
- 男の子の七五三は5歳だけする?お祝いする年齢や衣装を紹介
- 男の子の七五三をお祝いする年齢について詳しく紹介します。男の子が着る衣装の種類や七五三の基礎知識などを紹介します。
-
- 七五三を12月にずらしてもいい?メリットや注意点を解説
- 七五三の正式な時期や12月に行うメリットと注意点、12月以外のおすすめの時期を紹介します。
-
- 「七五三の挨拶マニュアル」ママパパも安心・文例やポイントを解説
- 七五三におけるシチュエーション別の挨拶の仕方や文例を知ることができます。
-
- 七五三のお食事会の手土産は何がおすすめ?主催者と参加者別に紹介
- 七五三手土産の対応方法やマナーについて解説します。
-
- 七五三の内祝いには何を選ぶ?のし紙や金額などのマナーを確認しよう
- 七五三の品選びのポイントとおすすめの品を解説します。
-
- 七五三を安く済ませるには?写真撮影の相場や費用を抑えるコツを紹介
- 七五三にかかる費用とその相場、記念写真撮影の費用を抑えるコツを紹介します。
-
- なぜ赤口は縁起が悪い?六曜とお祝いの日取りに関する基礎知識
- 赤口を中心に六曜の意味やそれぞれの特徴について詳しく解説します。
-
- 七五三の参拝はどこでやるのが正解?神社やお寺の選び方やマナー
- 七五三の基礎知識や参拝の場所、マナーや記念写真の撮影方法などを紹介します。
-
- 七五三に祖父母を呼ぶべき?注意点や呼ばない場合のマナーを知ろう
- 七五三に祖父母を呼ぶときの注意点や呼ぶか呼ばないかの判断、呼ばないときのマナーを紹介します。
-
- 7歳の七五三はいつ?年長でやるメリットや日取りの決め方を紹介
- 7歳の七五三をいつするか、準備の進め方や記念写真撮影をするタイミングの決め方などを紹介します。
-
- 七五三のお参りは夕方でもいい?縁起を担ぐ日取りの決め方とは
- 一般的な七五三の日時やお祝いの日程を決める際に役立つ参拝時期や撮影スケジュールの決め方を解説します。
-
- 七五三のトイレ問題を解決!スムーズに進めるためのアイテムやコツは?
- 七五三の3歳・5歳・7歳別のトイレ問題と対策などについて紹介します。
-
- 七五三の祝詞の意味とは?参拝に関する疑問を解決しよう
- 七五三の祝詞の意味に加え、ご祈祷に行く際のマナーや七五三の流れを紹介します。
-
- 七五三は全部の年齢でやるべき?お祝いの内容や費用をチェック
- 七五三の年齢や回数などを中心に詳しく解説します。
-
- 3歳・5歳・7歳の発達の目安は?七五三をお祝いする際の注意点
- 年齢ごとの発達の目安と、特徴について紹介します。
-
- 3歳児はかわいい!ママパパが癒やされた瞬間10選
- ママパパが癒やされる瞬間を紹介するほか、3歳児との愛情の育み方など、育児に役立つ情報もまとめました。
-
- 被布とは?3歳の七五三に着る意味やメリットを解説
- 被布とは何か、着るタイミングや年齢、着用するメリットについて解説します。
-
- 七五三で着る被布とは?選ぶポイントや着用時に必要なものを解説
- 被布とはどのようなものか、また七五三に被布を着用する際に選ぶポイントなどを詳しく解説します。
-
- 【2025年~2028年 早見表付き】七五三をお祝いする年齢と日程の決め方を紹介
- 2025年~2028年の七五三の早見表を紹介します。
-
- 七五三の参拝は六曜を気にしたほうがいい?六曜と神社やお寺の関係は?
- 七五三の日取りを決める際に六曜を気にしたほうがいいのかという点について深掘りします。
-
- 【2023年に七五三を迎えるママパパへ】お祝いの時期や準備リスト
- 2023年に七五三を迎えるお子さまは何年生まれなのか、お参りするおすすめの時期や準備リストなど、七五三をお祝いするために必要な情報をまるっと紹介します。
七五三で有名な神社
-
- 全国の七五三で有名な神社と、各地の風習(北海道・東北編)
- 七五三の参拝で有名な、北海道・青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島の神社を紹介します。
-
- 全国の七五三で有名な神社と、各地の風習(関東・北陸編)
- 七五三の参拝で有名な、新潟・富山・石川・福井・栃木・茨城・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川の神社を紹介します。
-
- 全国の七五三で有名な神社と、各地の風習(中部・関西編)
- 七五三の参拝で有名な、長野・岐阜・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山の神社を紹介します。
-
- 全国の七五三で有名な神社と、各地の風習(中国・四国編)
- 七五三の参拝で有名な、岡山・広島・山口・鳥取・島根・香川・徳島・愛媛・高知の神社を紹介します。
-
- 全国の七五三で有名な神社と、各地の風習(九州・沖縄編)
- 七五三の参拝で有名な、福岡・熊本・大分・佐賀・長崎・宮崎・鹿児島・沖縄の神社を紹介します。
-
- 【七五三】神社でご祈祷しないのはあり?お祝い方法や流れを紹介
- 七五三でご祈祷しない選択肢について考えます。
-
- 【お子さまのお祝い行事】神社にはいついく?参拝マナーもチェックしよう
- お子さまのお祝い行事の基本情報やマナーを紹介します。
あれこれ気になる「七五三事情」
-
- 七五三の準備って何をすればいいの?
- 参拝する神社や衣装のレンタル、食事会の予約まで、七五三の事前準備のコツを紹介します。
-
- 七五三の予算はいくらぐらいなの?
- 初めての七五三であれば一番気になるのがお金事情。先輩ママたちの七五三の予算についてアンケート調査をもとに解説します。
-
- 七五三をお祝いするための食事の段取り
- 七五三のお祝いで外食をしたり、お家でパーティーをする際の参考になるメニューについて紹介します。
-
- 七五三のお祝い金の相場はいくら?贈り方とお返しのマナーを解説
- 七五三に渡すお祝い金の相場を紹介します。
-
- 七五三といえば千歳飴!意味や由来、入手方法や食べ方をご紹介
- 千歳飴の由来や絵柄の意味、入手方法から食べ方までを紹介します。
-
- 七五三の当日が雨だった場合の対処法!お参りはできる?延期するべき?
- 七五三の当日に雨が降っても慌てないための準備や、延期する場合の注意点などをご紹介します。
-
- 七五三は仏滅の日にお祝いしてOK?七五三の日程の決め方を解説!
- 七五三を仏滅にしてもよいかを考えるため、この記事では六曜の意味を紹介します。
-
- 3歳の男の子も七五三で被布を着る?3歳で七五三のメリットも紹介
- 男の子が3歳でお祝いする魅力を紹介します。
-
- 七五三参り写真が映える!東京都内の神社・お寺10選|基礎知識も
- 七五三におすすめの東京都内の神社・お寺10選を紹介します。
-
- 七五三の神社や写真スタジオの予約方法・時期は?早めの準備が肝心!
- 七五三の神社ご祈祷予約や準備の時期など、準備段階で注意しておきたいことをご紹介します。
-
- 七五三は撮影のみでもOK?いつ撮影する?お祝いをスムーズにするポイント
- 七五三の本来の意味は、お子さまの成長を感謝し、これからの健やかな成長を願うというもの。できれば撮影のみという選択ではなく、神社やお寺でご祈祷もしたいものです。
-
- 七五三の料理はどうする?自宅でできるお祝いレシピも紹介
- 外食または自宅で食事会をする際のそれぞれのメリット・デメリットや、七五三の定番お祝い料理を紹介します。
-
- 男の子の七五三衣装|レンタルの魅力やおすすめの衣装を紹介
- 男の子の七五三衣装について徹底解説します。年齢別の衣装の選び方やレンタルと購入のメリット・デメリットを把握すれば、最適な方法で衣装を調達できるでしょう。
-
- 七五三はお寺でもOK?神社と違う参拝方法と人気の寺社を紹介
- お寺と神社のそれぞれの参拝方法を解説した上で、参拝先の決め方のポイントや七五三に人気の寺社を紹介します。
-
- 七五三の持ち物リスト|当日までに準備することを徹底解説
- 「七五三の持ち物リスト」や、当日までに準備することを紹介します。
-
- 七五三の父親のネクタイは何を選ぶ?色柄選びのポイントやおすすめコーデを紹介
- 七五三におすすめのパパのネクタイの色や柄、ネクタイを選ぶポイントやコーディネート例を紹介します。
-
- 七五三の初穂料はいくら必要?相場や書き方、渡し方のポイントを解説
- 七五三の初穂料の目安、渡し方や包み方について詳しく解説します。
-
- 七五三の絵馬の飾り方は?意味や処分方法なども詳しく解説
- 絵馬の飾り方や処分の仕方について解説します。
-
- 被布の読み方は?3歳の七五三で着る意味や選び方のポイントを解説
- 被布の読み方や意味、着用に適した年齢などを詳しく紹介します。
-
- 七五三での絵馬の書き方は?例文やポイント、保管方法を紹介
- 絵馬の書き方と記載時のポイントを紹介します。
-
- 七五三の千歳飴(ちとせあめ)に込められた願いとは?由来や食べ方を紹介
- 「七五三には千歳飴」となった理由や千歳飴の食べ方について解説します。
七五三の衣装・着物とヘアアレンジについて
-
- 3歳の七五三にぴったりの着物は?必要なものをチェックしよう
- 3歳の七五三の着物をクローズアップして解説します。
-
- 7歳の七五三を着物でお祝いしよう!必要なものや便利アイテムを紹介
- 7歳の七五三にふさわしい着物と着物に合わせる小物について解説します。
-
- 男の子の七五三はいつやる?3歳でお祝いするメリットや衣装、注意点をチェック
- 3歳の男の子の七五三について徹底解説。当日の流れや衣装、お祝いの仕方などを幅広く紹介します。
-
- 七五三で袴を着るときに必要なものは?ありがちなトラブルと対処法も
- 袴の着付けに必要なアイテムや装飾品、袴着用時のトラブル対処法など、七五三の袴に関する情報をまとめました。
-
- 七五三のママの服装はレンタルスーツが賢い!おすすめのスタイルは?
- レンタルスーツのメリットや七五三におすすめのスーツを紹介します。
-
- 七五三の家族写真は洋装・和装どちらにする?おすすめの服装を紹介
- 七五三の家族写真で着る服装を、洋装・和装に分けて紹介します。
-
- 3歳の七五三では髪型も重要!女の子と男の子の髪型アレンジのコツとは?
- 3歳の女の子の七五三での髪形アレンジのコツや、おすすめの髪形アレンジ例を紹介します。
-
- 七五三 男の子のヘアアレンジについて
- ほんの少し手を加えるだけで大きく変わる、男の子にぴったりなヘアアレンジについて紹介します。
-
- 7歳の七五三のかわいい髪型!画像で選べるおすすめ髪型17選
- 7歳におすすめの七五三髪型17選を画像と一緒に紹介します。
-
- 七五三はメイクでおめかし!3歳・7歳の化粧・髪型のポイントを解説
- きれいな衣装が着られる七五三はお子さまにとって特別な日。七五三におすすめのメイクを3歳と7歳に分けてご紹介します。
-
- 七五三の日本髪は桃割れが定番?新日本髪との違いや人気アレンジを紹介
- 「日本髪」や「桃割れ」をはじめとする、着物姿にぴったりな髪形について解説します。
-
- 3歳の七五三の着付け女の子・男の子の着付け方を紹介
- 3歳の七五三の着付けの仕方を女の子と男の子に分けて紹介します。
-
- 女の子・男の子の七五三の靴は?おでかけ靴の選び方や靴擦れ対策も
- 七五三のお出かけにぴったりの靴選びを押さえ、装いに合わせた靴選びのポイントや靴擦れ、鼻緒擦れの対処法も紹介します。
-
- 七五三のヘアメイク事情!年齢別におすすめの髪形とポイントを解説
- 七五三のヘアメイクについて年齢別に解説します。
-
- 産着は七五三用にお直しできる?男女別の仕立て直し方法や注意点
- 産着・祝着(のしめ)を七五三の着物へ仕立て直す方法について詳しく紹介します。
-
- 七五三|父親(パパ)の服装は?選び方やコーデ例・気になる疑問も解決!
- 父親(パパ)に焦点を当て、服装の選び方やコーデの例を紹介します。
-
- 【七五三】着物の着付け方&必要なものガイド|プロに依頼する方法も
- 七五三の着物の着付け方を簡単に分かりやすく解説します。
-
- 3歳の七五三に着物でお参り|必要なものや安心アイテムをチェック
- 3歳の着物の特徴や着付けに必要なものを紹介します。
-
- 【七五三】ドレス姿でプリンセス気分!3歳・7歳のドレス
- 3歳・7歳の女の子に向けたドレススタイルの例や、ドレスに合う髪型を紹介します。
-
- 3歳の七五三はツインテールがおすすめ!かわいさが引き立つアレンジ方法
- 七五三に合ったツインテールのアレンジ方法を紹介します。
-
- 着物の種類や格を知って、お子さまの節目に着物デビューをしよう!
- 着物や帯の種類・格について役立つ情報をご紹介します。
-
- 5歳の七五三で草履の代わりになる靴は?痛くならない方法や選び方
- 和装でお子さまが草履を履くときに足が痛くならないコツや、草履を履く前に準備しておくべきことについて解説します。
-
- 七五三の母親の着物はどう選ぶ?選び方やマナー、髪形や親子コーデも
- 七五三にふさわしいご両親の着物、着物を着る際の注意点やヘアスタイルを紹介します。
-
- 【3歳の七五三】女の子の髪形をかわいく!セルフでできる簡単アレンジを紹介
- 3歳のお子さま向けに簡単な髪形アレンジ方法を紹介します。
-
- 七五三の日本髪で失敗しないポイントは?年齢別の結い方も紹介
- 七五三の日本髪で失敗しないポイントを解説します。
-
- 七五三のママの髪形をおしゃれに!服装・長さ別におすすめを紹介
- 七五三にふさわしいママの髪形を紹介します。
-
- 7歳の七五三は着物姿で!ボブやショートにぴったりの髪形を紹介
- 着物姿にマッチするボブやショートにおすすめの髪形を紹介します。
-
- 3歳の七五三はワンピースでもOK?おすすめの服装とマナーを解説
- 七五三の服装に関するマナーや3歳におすすめの服装を紹介します。
-
- 七五三の髪飾りはどう選ぶ?3歳・7歳の和装にマッチするアイテムも紹介
- 七五三のコーディネートがよりステキに仕上がる髪飾りの選び方を解説します。
-
- 3歳の七五三|薄毛の女の子でもOK!セルフでできるおすすめの髪形
- 3歳の七五三におすすめの髪形を紹介します。
-
- 【5歳の七五三】羽織袴の着付け方は?必要なものやポイントを確認しよう
- 5歳の七五三で着用する羽織袴の着付け方について解説します。
七五三のスタジオ撮影と記念写真について
-
- 七五三の家族写真はスタジオ撮影がおすすめ!ママパパにおすすめの服装は?
- 七五三の家族写真を撮影する際に関するさまざまな情報をまとめて紹介します。
-
- 七五三のスタジオ撮影、「前撮り」と「同日撮り」のメリット・デメリット
- 「前撮り」「同日撮影」のメリット・デメリットについて、先輩ママたちへのアンケート調査より解説します。
-
- 七五三のスタジオ撮影で、思い出に残る写真アイテムとは
- お部屋に飾って楽しめるもの、プレゼントとして喜ばれるものなど、七五三におすすめな写真アイテムを紹介します。
-
- 七五三の前撮りはメリットがたくさん!おすすめの撮影時期とその理由を紹介!
- 前撮りのメリットやおすすめの時期、フォトスタジオ選びのポイントなどを紹介します。
-
- 七五三の写真はどこで撮影すると安い?大切な思い出をお得に残そう
- 七五三の写真撮影の依頼先や金額の目安、費用を抑えるポイントなどを紹介します。
-
- 七五三の写真はデータのみの購入は可能?自分でフォトブックを作る方法
- 七五三の写真データを保存するメリットを解説するとともに、七五三の思い出を形に残すアイデアについて紹介します。
-
- 七五三の後撮り撮影とは?おすすめの撮影時期やメリットを解説
- 後撮り撮影とはどのようなものなのか詳しく解説するとともに、おすすめの撮影時期メリットについても紹介します。
-
- 七五三の前撮り撮影はいつごろがおすすめ?時期ごとのメリットを確認しよう
- 前撮り撮影に適したタイミングや時期ごとの注意点を紹介します。


















![家族の思い出に、もっとフォーカス[PINTO]](/common/img/bnr_recommend_pinto.jpg)