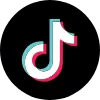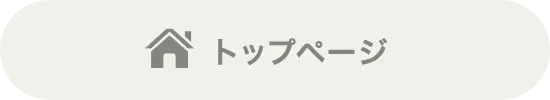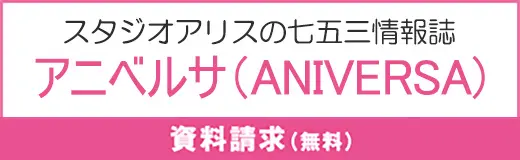七五三の意味や由来って?今さら聞けない基本的な疑問や流れ・服装を解決!|マタニティ、赤ちゃん、こどもの記念写真撮影ならこども写真館スタジオアリス|写真スタジオ・フォトスタジオ
七五三の意味や由来って?
今さら聞けない基本的な疑問や流れ・服装を解決!

七五三は昔からある日本の伝統行事です。一般的に参拝はは11月15日にするとされています。七五三のお祝いで、晴れ着姿のお子さまと神社にお参りに行くというご家庭も多いでしょう。七五三の由来は平安時代のころから宮中で行われてきた3つの儀式が基になっているそうです。儀式に必要な準備や手順をしっかり把握していたりする人は少ないのではないでしょうか。
この記事では、七五三の意味や参拝に行く場所、七五三の儀式に必要な準備や適切な服装などを解説します。また、七五三の記念撮影も可能なスタジオアリスの魅力についてもご紹介しますので、お子さまの健やかな成長を祝う七五三の儀式を行う際の参考にしてください。
- この記事でわかること
- 七五三の由来と儀式に込められた意味
- 七五三の準備の流れ
- 七五三の時期
- 目次
- 七五三にはどんな意味や由来がある?
- 七五三の参拝はどこに行けばいいの?
- 早めに準備しよう!七五三の儀式や流れ
- 七五三の服装とは?
- 七五三の時期はお子さまの成長に合わせて決めてOK
- 七五三ならスタジオアリス!スペシャルな思い出を残そう
- まとめ
七五三にはどんな意味や由来がある?

お子さまの健やかな成長を祝い、祈願する七五三は、その名の通り3歳、5歳、7歳で行われます。それぞれの年齢の儀式は名称や意味が異なり、男女で儀式をする年齢も異なります。
まずは七五三がいつから、どのような意味を込めて行われていたのか、また3つの儀式の持つ意味は何かを詳しくみていきましょう。
七五三の由来と儀式に込められた意味
七五三の由来には諸説ありますが、平安時代の頃から宮中で行われていた3つの儀式が基になっているそうです。現代に比べて医療の発達が未熟で衛生面もよくなかった昔は、子どもの死亡率がとても高く「7歳までは神のうち(神の子)」として扱われ、7歳になって初人として一人前であると認められていました。
子どもが無事に育つことは大きな喜びであり、親として健やかな成長を願わずにはいられないものでした。それゆえ、3歳、5歳、7歳の節目に成長を神様に感謝し、お祝いをしたことが七五三の由来とされており、やがて江戸時代に現在の七五三の原型として武家や商人の間に広まったといわれています。
それが明治時代には「七五三」と呼ばれて庶民にも広まり、大正時代以降に現在のような形ができあがったとされる説が有力です。
3歳・5歳・7歳を節目とした理由は、暦が中国から伝わった際に奇数は陽、つまり縁起がいいとされたためで、「3歳で言葉を理解し、5歳で知恵がつき、7歳で乳歯が生え替わる」という成長の節目の歳のためともいわれています。
なかでも7歳は「神のうち(神の子)」から人間として現世に完全に誕生する大きな祝いの歳とされていたため、七五三のなかでも7歳の儀式を重視する地方が多かったようです。
七五三は、地域によって独自に発展した側面もあり、少しずつ文化が違う場合もあります。起源となった儀式は以下の3つです。
3歳の男の子・女の子「髪置きの儀」
3歳の七五三は、平安時代、子どもの髪を伸ばし始める3歳の頃に行う儀式であった「髪置きの儀」が由来となっています。
平安時代の頃は男女ともに生後7日目に頭髪を剃り、3歳頃までは丸坊主で育てるという風習がありました。これは頭を清潔に保つことで病気の予防になり、のちに健康な髪が生えてくると信じられていたためです。
3歳の春を迎える頃に「髪置きの儀」を行われていたといわれておりました。子どもの健やかな成長や長生きを願い行う「髪置きの儀」は別名を「櫛置き」「髪立て」ともいい、長寿を祈願するために、白髪を模した白糸や綿白髪を頭上に置いて祝ったとも伝えられています。
5歳の男の子「袴着(はかまぎ)の儀」
5歳の七五三は、平安時代、5~7歳の頃に行われていた、当時の正装である袴を初めて身に付ける「袴着(はかまぎ)の儀」が由来となっています。
別名「着袴(ちゃっこ)」ともいわれるこの儀式を経て男の子は少年の仲間入りをし、羽織袴を身に付けたとされています。
当初は男女ともに行っていた儀式でしたが、江戸時代に男の子のみの儀式に変わりました。儀式はまず天下取りの意味を持つ碁盤の上に立って吉方に向き、縁起がいいとされる左足から袴を履きます。また冠をかぶって四方の神を拝んだともいわれており、四方の敵に勝つという願いが込められています。
現代の皇室でも、男児の儀式として数え5歳の時に「着袴(ちゃっこ)の儀」、その後に碁盤の上から飛び降りる「深曽木(ふかそぎ)の儀」が続けられています。この「深曽木(ふかそぎ)の儀」に倣い、碁盤の上から飛び降りる「碁盤の儀」を七五三詣の時期に開催している神社も全国各地にあります。
7歳の女の子「帯解(おびとき)の儀」
7歳の七五三は、鎌倉時代の頃に行われていた、着物を着る際に使っていた付け紐をとり、帯を初めて締める成長の儀式「帯解(おびとき)の儀」が由来となっています。
「帯解(おびとき)の儀」は室町時代に制定され、当初は男女ともに9際で行われていたとされています。
「帯解(おびとき)の儀」は別名「紐落し」「四つ身祝い」などと呼ばれますが、江戸時代に男児は5歳で「袴着(はかまぎ)の儀」を、女児は7歳で「帯解(おびとき)の儀」の行う形に変わり、この帯解を経て大人の女性へ歩み始めると認められていました。
七五三の参拝はどこに行けばいいの?
七五三の儀式では、お子さまの成長を感謝するため神社に参拝に行きます。一般的にはその土地を守ってくださる神様(氏神様)がいらっしゃる近所の神社へお参りに行くのがしきたりです。しかし最近は有名な神社に行くご家族も増えてきています。
もちろん近所の神社に限らず、歴史ある神社や景観の美しい神社、ご家族の思い出のある神社など、特別な思いのある場所にお参りに行くのもいいでしょう。しかし、あまり遠方の神社の場合、慣れない着物やフォーマルなワンピースを着たお子さまが疲れてしまうこともあります。
遠くの神社に行く際は、事前に天気予報やご祈祷の予約の有無、ご祈祷料、駐車場の場所などを確認しておきましょう。小さなお子さまが主役だということを忘れず、お子さまの負担にならない工夫が必要です。
早めに準備しよう!七五三の儀式や流れ

七五三の儀式の前には予約や準備など、しなければならないことが多く、「ご祈祷や着付け、写真撮影、衣装選び」などがあります。11月15日前後で行う場合には、遅くとも9月頃から準備をするのが一般的です。
お子さまの大切な記念日を安心して迎えられるよう、準備には余裕を持って取り掛かりましょう。
1.参拝する神社に予約する
神社でのご祈祷は予約が必要なことが多く、まずは参拝する神社に予約をします。七五三の参拝日は11月15日だといわれていますが、当日や前後の週末は混雑しやすいので夏頃までには予定を決め、9月初旬までに神社に連絡をするのがおすすめです。
両家の祖父母を招く際には、全員のスケジュールが合うことを重視し、11月の混雑期を外し、9月や10月、12月初旬に参拝に行くご家庭もあります。いずれにしても、早めにスケジュールを調整した方がよいでしょう。
予約の際にはご祈祷の内容や所要時間、初穂料、駐車場の有無なども確認します。のし袋やお賽銭用の小銭も当日までに準備しておくとスムーズです。
2.写真撮影の予約をする
出張カメラマンによる撮影、スタジオなどでの写真撮影を希望する場合は、撮影の予約も必要です。七五三当日の撮影も可能ですが、お子さまの体力やご家族のスケジュールなどを考慮し、別日に撮影をする人も少なくありません。
もちろん、七五三から大幅にずれた時期の撮影も可能です。お誕生日に、ご兄弟のお祝いと一緒に、混みあう時期を避けるなど、ご家族の都合のよいタイミングで撮影をしましょう。
スタジオによっては衣装のレンタルがある、着付けやセットをしてくれる、参拝の際に着物をレンタルしてくれるなどさまざまなサービスを提供してくれることもあります。
3.着付けやヘアメイクの予約をする
七五三では和装をするお子さまも多く、当日は着付けやヘアメイクも必要です。着付けとヘアメイクができる美容院を探し、遅くとも9月中旬頃までには予約をしましょう。小さなお子さまは、慣れない場所で不安になったり嫌がったりしてしまうこともあるかもしれません。行き慣れた美容院や、お子さまの対応が得意な美容院を選ぶのがおすすめです。
衣装をレンタルする場合、お店によっては着付けなどをしてくれることもありますので、予約時に確認してみましょう。
4.衣装の試着をする
七五三の1か月前頃には、実際に衣装を試着します。サイズ感などを確かめるのはもちろんですが、当日を想定しお子さまの動きもチェックするために、試着の際には足袋と草履も準備しましょう。
着物を着たら、足袋や草履も履き、上手に歩けるか確認します。また、七五三当日に「これを着てね」と衣装を見せると、嫌がってしまうお子さまもいます。日ごろから「着物を着てお参りに行こうね」と衣装を見せることで、お子さまも心の準備ができるのではないでしょうか。
5.カメラ・ビデオカメラ、初穂料を準備していざお詣りへ!
当日バタバタしないよう、前日までにカメラやビデオカメラのメモリーやバッテリー確認します。予備のバッテリー、メモリーカードを準備しておくのもおすすめです。また、タオルやお子さまの着替え、履き慣れた靴など持っていくものもチェックしましょう。
初穂料は新札を用意し、紅白蝶結びの水引のついたのし袋に入れます。下半分にはお子さまの名前、上半分は神社によって異なりますが、「初穂料」もしくは「玉串料」と記入してください。
お金は人物が表向き、上向きになるように中袋に入れます。中袋の表には「金〇〇円」と入っている金額を記入、裏の左下には住所と氏名を記入しましょう。中袋がない場合は、のし袋の裏側左下に金額と住所、氏名を書きます。
七五三の服装とは?

七五三の服装は、一般的には神様の前に出る儀式であるということを考慮し、お子さまもご家族も着物やスーツ、フォーマルワンピースなどを選ぶのがおすすめです。しかし、七五三は内祝いであるため、服装の決まりはないとされています。
カジュアルすぎないこと、肌の露出を控えることなど最低限のマナーを守ること、お子さまの年齢に最適なスタイルを選ぶことを意識して、季節や好みに合った服装を選びましょう。
子どもの服装
七五三では和装をするお子さまも多いですが、年齢ごとに種類の違う着物を着用します。
3歳の女の子は「三つ身」といって、帯はやわらかな兵児帯(へこおび)、さらに被布(ひふ)という袖のない上着を着るのが一般的です。小さなお子さまでも負担が少なく、着崩れしにくい仕様となっています。
7歳の女の子は「四つ身」という、子どもサイズの大人用の着物を着ますが、必要な小物や着付けの方法などは大人と同じです。着付けには襦袢や半襟、帯、帯揚げ、帯締めなど、また扇子や筥迫(はこせこ)などの小物が必要です。
男の子は3歳、5歳ともに「羽織袴」を着ますが、お宮参りで着た産着を仕立て直し、袴と一緒に使用することもあります。
また和装の場合、足元は足袋と草履です。慣れない草履では歩くのが大変なこともありますし、着物でのトイレも心配なため、ワンピースやスーツなどで神社に行くという方も少なくありません。特に小さなお子さまがいるご家庭は和装で前撮りをし、お参り当日は洋装ででかけることも多いようです。
両親の服装
七五三の主役はお子さまですので、ご家族がお子さまより目立ってしまうのはよいことだとはいえません。普段着のようなカジュアルすぎる服装もNGですが、目立ちすぎず、お子さまが引き立つような服装を心がけましょう。
ママは上品さや華やかさのある服装がおすすめです。お子さまのお世話などもあるため、動きやすいワンピースやセレモニースーツを着る方が多いですが、お子さまと合わせて和装をするという方もいます。和装の場合は略礼装の訪問着や色無地などを選びましょう。
パパはお子さまやお母様の服装に関係なく、スーツを着るのが一般的です。フォーマルなスーツでもお仕事で使用するスーツでも構いませんが、ダークカラーのものを選ぶとよいでしょう。シャツやネクタイは、シンプルななかにも華やかさのある色や柄だと、着物の横に並んでも遜色ありません。
また、ご家族の服装はお子さまよりも格下のものを選びますが、ご夫婦では格を合わせ、バランスをとるようにしましょう。
七五三の時期は子どもの成長に合わせて決めてOK

一般的に七五三の参拝は11月15日にするとされていますが、昨今はお子さまの成長に合わせて日程を決めるご家庭が増えています。数え年と満年齢のどちらで七五三をするか、どの時期に行うかなどはご家族で話し合い、お子さまの負担が少なく、機嫌のよい時間帯に撮影やお詣りに行くのがおすすめです。
そのために撮影とお詣りを別日で設定しても構いませんし、どちらかのみを行っても問題はありません。
七五三は当日にこだわらなくてもよい
七五三は11月15日当日にこだわらず前後してもよいですが、お祝い事なのでできれば前倒しでするのがおすすめです。前倒しの場合、10月中旬から11月頭にかけて参拝する方も多くいます。
他にも、9月に前撮りや参拝をするという方も多く、混雑しておらず日焼けをしていない肌で撮影できることから、記念撮影のみ夏前にするという方もいらっしゃいます。
各家庭に合った七五三をしよう
一昔前と比べると、七五三の時期や年齢については自由度が高くなっているので、撮影や参拝の時期は、各ご家庭に合わせ柔軟に変更しても問題はありません。
もともと女の子は3歳と7歳、男の子は3歳と5歳(5歳のみの地域もあり)でお祝いをしていましたが、最近は性別問わずすべての年齢でお祝いをする、兄弟の年齢に合わせ5歳の女の子や7歳の男の子もお祝いをするというパターンも増えています。
また、11月15日前後の参拝は人が多い可能性もあるため自粛し、記念撮影のみを行うご家や、七五三が「歳祝い」が始まりとされていることから、お子さまのお誕生日に七五三のお祝いをするご家庭もあります。ご家族で話し合い、最適なお祝いの形を見つけましょう。
七五三ならスタジオアリス!スペシャルな思い出を残そう

可愛い衣装でお子さまの晴れの日をお祝いしたいという気持ちは多くのママ・パパの願いです。そして、七五三の行事の際、お子さまが長時間衣装を着ることが難しかったり、レンタル衣装を汚してしまったりするかもしれないと不安があるお父様、お母様も多いでしょう。
スタジオアリスの七五三撮影は、お子さまの撮影に慣れているプロのカメラマン、バリエーション豊富な衣装、七五三のおでかけ衣装レンタルなど、魅力がたくさんあります。
また、店内の消毒、換気、スタッフの検温やマスク着用を徹底し、感染予防対策は万全です。コロナ禍でも安心、安全に七五三の思い出を残していただけます。
お気に入りが見つかる豊富な衣装ラインアップ
七五三の衣装は約190着と、年齢や性別に合わせて豊富に用意しています。お好きな衣装を複数お選びいただけ、和装、洋装両方の撮影が可能です。
また、七五三の和装には人気キャラクターとのコラボ衣装もあります。大好きなキャラクターをあしらったデザインの衣装を着ることで、お子さまもより撮影を楽しめるのではないでしょうか。
衣装レンタルはもちろん、スタジオアリスでは着付けやヘアセットもトータルでお仕上げいたします。そのため、来店時は普段着でよいのも魅力のひとつです。また、和装と洋装の組み合わせなど、お好きな衣装を複数選んでの撮影が可能です。おひとりで、ご兄弟で、ご家族と、さまざまなポーズで撮影をお楽しみください。
おでかけ衣装もレンタルできる
撮影だけでなく神社にも着物で、という方には、おでかけ用着物のレンタルもしています。
撮影時に着た衣装とは違うものを選ぶこともできるので、撮影とお出かけ、2種類の和装が楽しめます。もちろん、人気ブランドやキャラクター衣装からもお選びいただけます。
また、撮影時だけでなく、おでかけ当日の着付けやヘアセットも無料で、草履や小物もレンタル可能です。おでかけレンタルの際も、ご自宅でのヘアセットといった準備は必要なく、普段着でご来店いただけます。
大人気のパパママ着物フォトプラン
着物は日本の伝統的な衣装ですが、日常的に着るという方は少ないでしょう。しかし七五三の撮影では、ママだけでなくパパも含めたご家族みんなで、普段着ることのない和装でお祝いするというご家庭も増えてきました。
スタジオアリスでもママ・パパに気軽に和装をお楽しみいただけるよう、「パパママ着物フォトプラン」を用意しています。ママ・パパも手ぶらでご来店いただき、着付けはもちろん着物から小物まですべてレンタル可能です。
ご家族そろっての和装という貴重な機会を、ぜひスタジオアリスで写真に残してはいかがでしょうか。
(参考:『スタジオアリス』ホームページ)
まとめ

平安時代に行われていた「髪置きの儀」「袴着の儀」「帯解きの儀」という3つの儀式に由来する七五三は、現代でもお子さまの健やかな成長をお祝いするおめでたい行事として根強く残っています。
七五三では記念撮影とご祈祷をするのが一般的ですが、11月15日前後は神社も写真スタジオも混みあうため、早めに予約や準備をしましょう。お子さまの成長やご家庭の予定に合わせ七五三の時期をずらすことも可能です。
スタジオアリスでは和装、洋装ともに豊富なバリエーションの衣装、さまざまプランを用意しています。
お出かけ用の着物レンタルやご家族そろっての和装撮影もできますので、ぜひお子さまの成長をお祝いする記念撮影をお楽しみください。
七五三コラム一覧
七五三のキホン
-
- 七五三の意味や由来って?今さら聞けない基本的な疑問や流れ・服装を解決!
- 七五三の意味や参拝に行く場所、七五三の儀式に必要な準備や適切な服装などを紹介します。
-
- 女の子の七五三はいつやるの?可愛さ引き立つ女の子向け衣装の選び方やおすすめの時期
- 女の子が七五三をするタイミングや一般的な流れ、衣装の選び方などを紹介します。
-
- 七五三って何をする行事?基礎知識から気になる疑問をまとめて解説!
- 七五三をお祝いする時期や当日の流れ、必要な持ち物を紹介しながら、七五三はいったい何をする行事なのか詳しく説明します。
-
- 七五三をお祝いしよう!年齢ごとの衣装選びや準備、3歳の七五三をスムーズにするコツも◎
- 七五三について年齢別のおすすめ衣装や準備のポイントと併せて、やんちゃ盛りのお子さまでも楽しく、かつスムーズにお祝いの日を過ごせるコツを紹介します。
-
- 七五三を兄弟姉妹で同時にするメリット|服装・写真撮影を徹底ガイド
- 兄弟姉妹で一緒にする場合のメリットを解説しながら、当日の服装や写真撮影についてご紹介します。
-
- 七五三当日の流れは?記念写真撮影は前撮り・後撮りも活用しよう
- 七五三当日の流れや、スムーズなお祝いをするためにおすすめしたいスタジオアリスの七五三撮影の魅力をご紹介します。
-
- 男の子の七五三は5歳だけする?お祝いする年齢や衣装を紹介
- 男の子の七五三をお祝いする年齢について詳しく紹介します。男の子が着る衣装の種類や七五三の基礎知識などを紹介します。
-
- 七五三を12月にずらしてもいい?メリットや注意点を解説
- 七五三の正式な時期や12月に行うメリットと注意点、12月以外のおすすめの時期を紹介します。
-
- 「七五三の挨拶マニュアル」ママパパも安心・文例やポイントを解説
- 七五三におけるシチュエーション別の挨拶の仕方や文例を知ることができます。
-
- 七五三のお食事会の手土産は何がおすすめ?主催者と参加者別に紹介
- 七五三手土産の対応方法やマナーについて解説します。
-
- 七五三の内祝いには何を選ぶ?のし紙や金額などのマナーを確認しよう
- 七五三の品選びのポイントとおすすめの品を解説します。
-
- 七五三を安く済ませるには?写真撮影の相場や費用を抑えるコツを紹介
- 七五三にかかる費用とその相場、記念写真撮影の費用を抑えるコツを紹介します。
-
- なぜ赤口は縁起が悪い?六曜とお祝いの日取りに関する基礎知識
- 赤口を中心に六曜の意味やそれぞれの特徴について詳しく解説します。
-
- 七五三の参拝はどこでやるのが正解?神社やお寺の選び方やマナー
- 七五三の基礎知識や参拝の場所、マナーや記念写真の撮影方法などを紹介します。
-
- 七五三に祖父母を呼ぶべき?注意点や呼ばない場合のマナーを知ろう
- 七五三に祖父母を呼ぶときの注意点や呼ぶか呼ばないかの判断、呼ばないときのマナーを紹介します。
-
- 7歳の七五三はいつ?年長でやるメリットや日取りの決め方を紹介
- 7歳の七五三をいつするか、準備の進め方や記念写真撮影をするタイミングの決め方などを紹介します。
-
- 七五三のお参りは夕方でもいい?縁起を担ぐ日取りの決め方とは
- 一般的な七五三の日時やお祝いの日程を決める際に役立つ参拝時期や撮影スケジュールの決め方を解説します。
-
- 七五三のトイレ問題を解決!スムーズに進めるためのアイテムやコツは?
- 七五三の3歳・5歳・7歳別のトイレ問題と対策などについて紹介します。
-
- 七五三の祝詞の意味とは?参拝に関する疑問を解決しよう
- 七五三の祝詞の意味に加え、ご祈祷に行く際のマナーや七五三の流れを紹介します。
-
- 七五三は全部の年齢でやるべき?お祝いの内容や費用をチェック
- 七五三の年齢や回数などを中心に詳しく解説します。
-
- 3歳・5歳・7歳の発達の目安は?七五三をお祝いする際の注意点
- 年齢ごとの発達の目安と、特徴について紹介します。
-
- 3歳児はかわいい!ママパパが癒やされた瞬間10選
- ママパパが癒やされる瞬間を紹介するほか、3歳児との愛情の育み方など、育児に役立つ情報もまとめました。
-
- 被布とは?3歳の七五三に着る意味やメリットを解説
- 被布とは何か、着るタイミングや年齢、着用するメリットについて解説します。
-
- 七五三で着る被布とは?選ぶポイントや着用時に必要なものを解説
- 被布とはどのようなものか、また七五三に被布を着用する際に選ぶポイントなどを詳しく解説します。
-
- 【2025年~2028年 早見表付き】七五三をお祝いする年齢と日程の決め方を紹介
- 2025年~2028年の七五三の早見表を紹介します。
-
- 七五三の参拝は六曜を気にしたほうがいい?六曜と神社やお寺の関係は?
- 七五三の日取りを決める際に六曜を気にしたほうがいいのかという点について深掘りします。
-
- 【2023年に七五三を迎えるママパパへ】お祝いの時期や準備リスト
- 2023年に七五三を迎えるお子さまは何年生まれなのか、お参りするおすすめの時期や準備リストなど、七五三をお祝いするために必要な情報をまるっと紹介します。
七五三で有名な神社
-
- 全国の七五三で有名な神社と、各地の風習(北海道・東北編)
- 七五三の参拝で有名な、北海道・青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島の神社を紹介します。
-
- 全国の七五三で有名な神社と、各地の風習(関東・北陸編)
- 七五三の参拝で有名な、新潟・富山・石川・福井・栃木・茨城・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川の神社を紹介します。
-
- 全国の七五三で有名な神社と、各地の風習(中部・関西編)
- 七五三の参拝で有名な、長野・岐阜・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山の神社を紹介します。
-
- 全国の七五三で有名な神社と、各地の風習(中国・四国編)
- 七五三の参拝で有名な、岡山・広島・山口・鳥取・島根・香川・徳島・愛媛・高知の神社を紹介します。
-
- 全国の七五三で有名な神社と、各地の風習(九州・沖縄編)
- 七五三の参拝で有名な、福岡・熊本・大分・佐賀・長崎・宮崎・鹿児島・沖縄の神社を紹介します。
-
- 【七五三】神社でご祈祷しないのはあり?お祝い方法や流れを紹介
- 七五三でご祈祷しない選択肢について考えます。
-
- 【お子さまのお祝い行事】神社にはいついく?参拝マナーもチェックしよう
- お子さまのお祝い行事の基本情報やマナーを紹介します。
あれこれ気になる「七五三事情」
-
- 七五三の準備って何をすればいいの?
- 参拝する神社や衣装のレンタル、食事会の予約まで、七五三の事前準備のコツを紹介します。
-
- 七五三の予算はいくらぐらいなの?
- 初めての七五三であれば一番気になるのがお金事情。先輩ママたちの七五三の予算についてアンケート調査をもとに解説します。
-
- 七五三をお祝いするための食事の段取り
- 七五三のお祝いで外食をしたり、お家でパーティーをする際の参考になるメニューについて紹介します。
-
- 七五三のお祝い金の相場はいくら?贈り方とお返しのマナーを解説
- 七五三に渡すお祝い金の相場を紹介します。
-
- 七五三といえば千歳飴!意味や由来、入手方法や食べ方をご紹介
- 千歳飴の由来や絵柄の意味、入手方法から食べ方までを紹介します。
-
- 七五三の当日が雨だった場合の対処法!お参りはできる?延期するべき?
- 七五三の当日に雨が降っても慌てないための準備や、延期する場合の注意点などをご紹介します。
-
- 七五三は仏滅の日にお祝いしてOK?七五三の日程の決め方を解説!
- 七五三を仏滅にしてもよいかを考えるため、この記事では六曜の意味を紹介します。
-
- 3歳の男の子も七五三で被布を着る?3歳で七五三のメリットも紹介
- 男の子が3歳でお祝いする魅力を紹介します。
-
- 七五三参り写真が映える!東京都内の神社・お寺10選|基礎知識も
- 七五三におすすめの東京都内の神社・お寺10選を紹介します。
-
- 七五三の神社や写真スタジオの予約方法・時期は?早めの準備が肝心!
- 七五三の神社ご祈祷予約や準備の時期など、準備段階で注意しておきたいことをご紹介します。
-
- 七五三は撮影のみでもOK?いつ撮影する?お祝いをスムーズにするポイント
- 七五三の本来の意味は、お子さまの成長を感謝し、これからの健やかな成長を願うというもの。できれば撮影のみという選択ではなく、神社やお寺でご祈祷もしたいものです。
-
- 七五三の料理はどうする?自宅でできるお祝いレシピも紹介
- 外食または自宅で食事会をする際のそれぞれのメリット・デメリットや、七五三の定番お祝い料理を紹介します。
-
- 男の子の七五三衣装|レンタルの魅力やおすすめの衣装を紹介
- 男の子の七五三衣装について徹底解説します。年齢別の衣装の選び方やレンタルと購入のメリット・デメリットを把握すれば、最適な方法で衣装を調達できるでしょう。
-
- 七五三はお寺でもOK?神社と違う参拝方法と人気の寺社を紹介
- お寺と神社のそれぞれの参拝方法を解説した上で、参拝先の決め方のポイントや七五三に人気の寺社を紹介します。
-
- 七五三の持ち物リスト|当日までに準備することを徹底解説
- 「七五三の持ち物リスト」や、当日までに準備することを紹介します。
-
- 七五三の父親のネクタイは何を選ぶ?色柄選びのポイントやおすすめコーデを紹介
- 七五三におすすめのパパのネクタイの色や柄、ネクタイを選ぶポイントやコーディネート例を紹介します。
-
- 七五三の初穂料はいくら必要?相場や書き方、渡し方のポイントを解説
- 七五三の初穂料の目安、渡し方や包み方について詳しく解説します。
-
- 七五三の絵馬の飾り方は?意味や処分方法なども詳しく解説
- 絵馬の飾り方や処分の仕方について解説します。
-
- 被布の読み方は?3歳の七五三で着る意味や選び方のポイントを解説
- 被布の読み方や意味、着用に適した年齢などを詳しく紹介します。
-
- 七五三での絵馬の書き方は?例文やポイント、保管方法を紹介
- 絵馬の書き方と記載時のポイントを紹介します。
-
- 七五三の千歳飴(ちとせあめ)に込められた願いとは?由来や食べ方を紹介
- 「七五三には千歳飴」となった理由や千歳飴の食べ方について解説します。
七五三の衣装・着物とヘアアレンジについて
-
- 3歳の七五三にぴったりの着物は?必要なものをチェックしよう
- 3歳の七五三の着物をクローズアップして解説します。
-
- 7歳の七五三を着物でお祝いしよう!必要なものや便利アイテムを紹介
- 7歳の七五三にふさわしい着物と着物に合わせる小物について解説します。
-
- 男の子の七五三はいつやる?3歳でお祝いするメリットや衣装、注意点をチェック
- 3歳の男の子の七五三について徹底解説。当日の流れや衣装、お祝いの仕方などを幅広く紹介します。
-
- 七五三で袴を着るときに必要なものは?ありがちなトラブルと対処法も
- 袴の着付けに必要なアイテムや装飾品、袴着用時のトラブル対処法など、七五三の袴に関する情報をまとめました。
-
- 七五三のママの服装はレンタルスーツが賢い!おすすめのスタイルは?
- レンタルスーツのメリットや七五三におすすめのスーツを紹介します。
-
- 七五三の家族写真は洋装・和装どちらにする?おすすめの服装を紹介
- 七五三の家族写真で着る服装を、洋装・和装に分けて紹介します。
-
- 3歳の七五三では髪型も重要!女の子と男の子の髪型アレンジのコツとは?
- 3歳の女の子の七五三での髪形アレンジのコツや、おすすめの髪形アレンジ例を紹介します。
-
- 七五三 男の子のヘアアレンジについて
- ほんの少し手を加えるだけで大きく変わる、男の子にぴったりなヘアアレンジについて紹介します。
-
- 7歳の七五三のかわいい髪型!画像で選べるおすすめ髪型17選
- 7歳におすすめの七五三髪型17選を画像と一緒に紹介します。
-
- 七五三はメイクでおめかし!3歳・7歳の化粧・髪型のポイントを解説
- きれいな衣装が着られる七五三はお子さまにとって特別な日。七五三におすすめのメイクを3歳と7歳に分けてご紹介します。
-
- 七五三の日本髪は桃割れが定番?新日本髪との違いや人気アレンジを紹介
- 「日本髪」や「桃割れ」をはじめとする、着物姿にぴったりな髪形について解説します。
-
- 3歳の七五三の着付け女の子・男の子の着付け方を紹介
- 3歳の七五三の着付けの仕方を女の子と男の子に分けて紹介します。
-
- 女の子・男の子の七五三の靴は?おでかけ靴の選び方や靴擦れ対策も
- 七五三のお出かけにぴったりの靴選びを押さえ、装いに合わせた靴選びのポイントや靴擦れ、鼻緒擦れの対処法も紹介します。
-
- 七五三のヘアメイク事情!年齢別におすすめの髪形とポイントを解説
- 七五三のヘアメイクについて年齢別に解説します。
-
- 産着は七五三用にお直しできる?男女別の仕立て直し方法や注意点
- 産着・祝着(のしめ)を七五三の着物へ仕立て直す方法について詳しく紹介します。
-
- 七五三|父親(パパ)の服装は?選び方やコーデ例・気になる疑問も解決!
- 父親(パパ)に焦点を当て、服装の選び方やコーデの例を紹介します。
-
- 【七五三】着物の着付け方&必要なものガイド|プロに依頼する方法も
- 七五三の着物の着付け方を簡単に分かりやすく解説します。
-
- 3歳の七五三に着物でお参り|必要なものや安心アイテムをチェック
- 3歳の着物の特徴や着付けに必要なものを紹介します。
-
- 【七五三】ドレス姿でプリンセス気分!3歳・7歳のドレス
- 3歳・7歳の女の子に向けたドレススタイルの例や、ドレスに合う髪型を紹介します。
-
- 3歳の七五三はツインテールがおすすめ!かわいさが引き立つアレンジ方法
- 七五三に合ったツインテールのアレンジ方法を紹介します。
-
- 着物の種類や格を知って、お子さまの節目に着物デビューをしよう!
- 着物や帯の種類・格について役立つ情報をご紹介します。
-
- 5歳の七五三で草履の代わりになる靴は?痛くならない方法や選び方
- 和装でお子さまが草履を履くときに足が痛くならないコツや、草履を履く前に準備しておくべきことについて解説します。
-
- 七五三の母親の着物はどう選ぶ?選び方やマナー、髪形や親子コーデも
- 七五三にふさわしいご両親の着物、着物を着る際の注意点やヘアスタイルを紹介します。
-
- 【3歳の七五三】女の子の髪形をかわいく!セルフでできる簡単アレンジを紹介
- 3歳のお子さま向けに簡単な髪形アレンジ方法を紹介します。
-
- 七五三の日本髪で失敗しないポイントは?年齢別の結い方も紹介
- 七五三の日本髪で失敗しないポイントを解説します。
-
- 七五三のママの髪形をおしゃれに!服装・長さ別におすすめを紹介
- 七五三にふさわしいママの髪形を紹介します。
-
- 7歳の七五三は着物姿で!ボブやショートにぴったりの髪形を紹介
- 着物姿にマッチするボブやショートにおすすめの髪形を紹介します。
-
- 3歳の七五三はワンピースでもOK?おすすめの服装とマナーを解説
- 七五三の服装に関するマナーや3歳におすすめの服装を紹介します。
-
- 七五三の髪飾りはどう選ぶ?3歳・7歳の和装にマッチするアイテムも紹介
- 七五三のコーディネートがよりステキに仕上がる髪飾りの選び方を解説します。
-
- 3歳の七五三|薄毛の女の子でもOK!セルフでできるおすすめの髪形
- 3歳の七五三におすすめの髪形を紹介します。
-
- 【5歳の七五三】羽織袴の着付け方は?必要なものやポイントを確認しよう
- 5歳の七五三で着用する羽織袴の着付け方について解説します。
七五三のスタジオ撮影と記念写真について
-
- 七五三の家族写真はスタジオ撮影がおすすめ!ママパパにおすすめの服装は?
- 七五三の家族写真を撮影する際に関するさまざまな情報をまとめて紹介します。
-
- 七五三のスタジオ撮影、「前撮り」と「同日撮り」のメリット・デメリット
- 「前撮り」「同日撮影」のメリット・デメリットについて、先輩ママたちへのアンケート調査より解説します。
-
- 七五三のスタジオ撮影で、思い出に残る写真アイテムとは
- お部屋に飾って楽しめるもの、プレゼントとして喜ばれるものなど、七五三におすすめな写真アイテムを紹介します。
-
- 七五三の前撮りはメリットがたくさん!おすすめの撮影時期とその理由を紹介!
- 前撮りのメリットやおすすめの時期、フォトスタジオ選びのポイントなどを紹介します。
-
- 七五三の写真はどこで撮影すると安い?大切な思い出をお得に残そう
- 七五三の写真撮影の依頼先や金額の目安、費用を抑えるポイントなどを紹介します。
-
- 七五三の写真はデータのみの購入は可能?自分でフォトブックを作る方法
- 七五三の写真データを保存するメリットを解説するとともに、七五三の思い出を形に残すアイデアについて紹介します。
-
- 七五三の後撮り撮影とは?おすすめの撮影時期やメリットを解説
- 後撮り撮影とはどのようなものなのか詳しく解説するとともに、おすすめの撮影時期メリットについても紹介します。
-
- 七五三の前撮り撮影はいつごろがおすすめ?時期ごとのメリットを確認しよう
- 前撮り撮影に適したタイミングや時期ごとの注意点を紹介します。















![家族の思い出に、もっとフォーカス[PINTO]](/common/img/bnr_recommend_pinto.jpg)